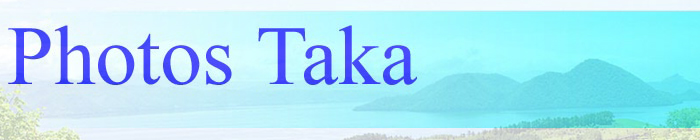|
1. 心の存在
全ての生命は、生命であることによって、欲求、欲望を持っている。
生命を維持、存続させようとして、欲求、欲望を持つのが、生命の宿命、自然の姿である。
その欲望の存在が、すなわち、意識の存在となり、人間の場合、心の存在となった。
心とは、物理的な存在ではない。
しかし、人間の肉体の存在が物理的に確かな存在であるのと同じく、人間の心の存在も、その個体が生命を宿し、意識を持つ限りにおいて、確かなものであると考える。
2.「少年性」と「少女性」
人間の心の様相として、私は、「少年性」と「少女性」という用語を用いて、二つの様相があると考える。
3.「少年性」
「少年性」とは何か。
私は、「少年性」という言葉によって、人間の心の(または、生命の欲望の)うちの、原初的、単独的な様相を捉えたいと考える。
原初的、単独的な様相。
すなわち、それは、自己中心的であり、即物的であり、闘争的であり、粗暴である心の様相である。
それは、あたかも、この世に自分ひとりしか存在しないかのようにして、自己の欲望を満たそうと考え、振舞おうとする心の傾向、様相である。
それは、例えて言えば、いたずら好きな腕白小僧のイメージである。
五つの要素が考えられる。
〇 自己中心性
〇 闘争性
〇 粗暴性
〇 即物性
〇 即物的空想性
☆
〇 自己中心性
全ての意識の中心は、自己である。
意識を持つものの全てにおいて、その中心は、自己である。
従って、自己を唯一の主体であるかのようにして、世界を見、世界に対応しようとするのが、意識の第一の行動傾向となる。
主体は自分だけ、他はすべて客体であるから、自分を取り巻く世界とは、行動の対象となるだけの存在であるとみなすという意識のあり方のことである。
それは、また、自分以外のものになり代わって考えるという想像上の同化・共感ということをしない意識とも言える。
意識は、すべてこのような自己中心性を持つ。
〇 闘争性
生命の生存欲求から来る闘争本能に由来する闘争性である。
それは、自己の存在をもっとも大切なものとする意識、自己の生存を守ろうとする意識から生まれてくる。
自己の存在のみを尊重する意識だからこそ、自己を守るために闘うのである。
〇 粗暴性
自己の欲求だけを意識する意識、他との関係を重視しない意識、自己の存在だけを尊重する傾向の意識であるために、その行動は、他からどのように受け取られるかを考えない、他との協調を考えないという傾向にある。
それが、粗暴ということになる。
自分勝手な振る舞いということである。
〇 即物性
自分を取り巻く世界を対象としてのみ捉える傾向にある意識は、対象を物質的にのみ捉える傾向にある。なにもかも物質的に捉える。
他の人間をも物質的に捉える。
幸福感をも物質的に捉えられるかのように思う。
お酒をたくさん飲むことが幸福だと考えるようなこと。
〇 即物的空想性
物質的な存在を機縁として、空想をし、その空想を広げていくのが、即物的空想性である。
「少年性」においての空想は、ほとんどが即物的であるとも言うことができると考える。物質的に空想を広げていくことである。人の心の内を想像することの対極にあるとも言える。
即物的であることによって、合理的な思考に近づくこともある。
しかし、即物的であるからといって、即、合理的であることにはならない。
即物的であることは、表面的である傾向が強く、表面的であることで、合理性を捉えそこなうことはよくあることである。
4.「少年性」の原初性
この「少年性」というのは、少年に顕著に認められるけれども、少年だけの性質ではない。
実際の少女にも認められる性質である。
この「少年性」は、人間の心の生物としての原初性であると考える。
従って、その性が男性であるか、女性であるかに関わらず、人の心に初めから備わっている性質であると考える。
ならば、その性質は、「少年性」などと、少年だけにあるかのような誤解を招く言い方をせず、「原初性」のように、性別を離れた言い方をした方がわかり易いのではないか。
それは、そうなのだが、なお、私は、これを「少年性」と呼びたい。
なぜならば、やはりこの「少年性」は、性別に関わらず認められる原初的なものなのだけれども、少年の方に、より顕著に現れ、認められるものだと思うからである。
少女の中にも、この「少年性」を色濃く現す個人が認められる。
しかし、はるかに多く、少年の方に、この「少年性」は、その姿を現すと、私は考えている。
5.「少女性」
「少女性」とは何か。
私の言う「少女性」とは、言い換えるならば、「関係性」である。
「社会性の始まり」とも言える。
私は、この「少女性」という言葉によって、特に少女に顕著に現れる心の様相を捉えようとしているのだが、それは、お人形遊びをする少女のイメージである。
実際の少年の中にも、お人形遊びをする少年はいるだろう。しかし、それはごく稀なことではないか。
はるかに多く、少女において、お人形遊びは認められることである、と考える。
そのお人形遊びは、いかにして生じるのであるか。
おそらく、自分の世話をする母親やその他の大人と、自分との関係から生じてくるに違いない。
お人形遊びは、社会的な遊び、つまり、関係というものと深く結びついた遊びであると捉える。
そのお人形遊びをする少女のイメージから、私は、「少女性」として、五つの要素を捉える。
〇
同化・共感性
〇
親和性
〇
柔和性
〇
夢想性
〇
空想的解釈性
☆
〇 同化・共感性
対象に、自分が成り代わってしまうほどの共感性である。
それは、あくまでも想像上のことであるのだが、自分以外の対象物、他人とか物とか、その対象物になり切って(と本人が信じて)、こうだ、ああだと考えたり、感じたりするという性質。
お人形遊びをする少女で説明すれば、自分が、対象のお人形になり切って感じたり、考えたりするということである。
相手の身になって考えるということの基本は、ここにあると考える。
〇 親和性
親和性とは、対象と親しみ、平和的な関係を作ろうとする性質。
対象との間に親しみのある関係を作ろうとする。
親しみのある関係とは、平和的な関係である。
お人形遊びで説明すれば、それは、お人形を大切にすることを意味する。お人形に親しみ、お人形を自分と対等の存在のように考えて、大切に扱う。
対象が人であれば、その人と争うような関係にならず、平和的で、親しみのある、相手のことをわがことのように考える関係に立とうとすることである。
〇 柔和性
柔和性とは、少女が、その周りに物柔らかな雰囲気を漂わすことである。
そのような作用をもっているのは、少女に顕著に見られることだと考えるので、「少女性」のひとつとして「柔和性」を捉えたい。
だが、それは、母親が乳児に対する時に自然に漂わすと思われる雰囲気である。
柔和性とは、「少年性」の「粗暴性」と対比的関係にある性質である。
周囲との関係を大切にする意識から、周囲との関係を物柔らかなものに保とうとする力を発揮すること。
〇 夢想性
この夢想性は、関係の中での夢想、空想である。
それは、あるものと自分との関係、ある人と自分との関係で、空想に耽ることである。
しかも、その空想を、夢を見ている時、それがあたかも現実であるかのように信じることがあるように、この夢想は、現実に重ね合わされ、しばしば、現実と混同されることもある。
そのような夢想をする能力である。
だが、これには大概、自覚がある。夢想しているという自覚がある。
お人形遊びをする少女は、あたかも人形が生きているかのように扱う。しかし、それは遊びでそうしていることを自覚している。人形が生きていると信じているわけではない、が、時に、まったく生きているかのように扱ってしまうこともある。
〇 空想的解釈性
現実の理解を、即物的に行うのではなく、空想的な解釈をすることで、理解していると思う傾向のことである。
そのためにしばしば非論理的な解釈を行う。
自分の空想・夢想が勝っているからである。
夢想性と区別するのは、空想で現実を解釈しているということに無自覚である点に違いがある。
自覚がないので、それが勝手な空想であることに気づかせるのは難しい。
非論理的な解釈をしながら、それが現実を理解していることだとする傾向のことである。
|