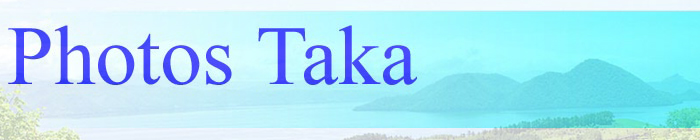|
〇誕生とは、何か。
誕生とは、分離である。
自己という存在が、世界から分離して、存在することであり、それは自己にとって、世界に対峙して認識されるようになること、である。
誕生とは、世界からの分離である。
世界から分離することによって、世界を認識することができるようになるのである。
よって、私の誕生とは、私が、世界から分離した、ということを意味する。
それがまた、私の存在に、根本的に潜在する、不安や恐怖の原因である。
〇世界の誕生とは、何か。
誕生が、世界からの分離あるとすると、世界の誕生とは、何からの分離であるのか。
全ての存在は、それ自身から誕生することはできない。
全ては、非自身からの誕生なのである。
すると、世界は、非世界からの分離ということになる。
非世界とは、どういうものか。
世界が、物質ででき、物理法則に支配されているとするならば、非世界とは、非物質ででき、物理法則に非ざるものに支配されたものということになる。
非世界とは、非物質ででき、非物理法則に支配されたものである。
〇「命」は、個体に宿る。
「命」は、個体に宿るものである。個体に宿るのではない「命」は、可能性の「命」として、観念として認識できるものでしかない。それは、現実的な存在ではない。現実的な存在としての「命」は、必ず、個体として存在する。単細胞であるか、多細胞であるかの違いはあっても、個体として存在するものであって、個体として存在するのではない「命」を考えるのは、あくまで観念的な「命」の概念でしかない。
「命」は、個体に宿る。
それゆえに、「命」は、個性を持つものとなる。また、それゆえに、主体性を持つのである。
〇「原罪」とは、何か。
私の考える「原罪」とは、命を保つために、他の命を奪うことである。すなわち、自分の命を保ち、養うために、食物として、植物にしろ、動物にしろ、他の命を殺し、摂取することである。
それこそが、本来的な「原罪」、ほとんどの植物などの自立栄養生命体ではない、他立栄養生命体の根本的な「罪」、「原罪」である、と考える。
では、それに対する、「贖罪」とは、何か。
それが、問題なのである。
その答えのひとつとして考えることは、科学技術の進化で、いつの日か、植物のように自立栄養が可能になれば、「原罪」から解放されるだろう、ということである。
それは、例えば、無機物と光合成から、栄養物の生成、アミノ酸の生成が、工業的に、安価に可能になれば、達成できるのではないか、と考える。
だが、これは、自然からの乖離になってしまうものなのか。自然の恵みを拒否しているようなものなのか。無機物と光であっても、自然の恵みではないか、と考えれば、無機物と光からアミノ酸を工業的に生成しても、自然の恵みを受けているものに違いないと言える筈だ、とも考えられる。
だが、その場合に、植物などの自然生成由来のものに劣るものしか生成できないのであれば、それに取り替えることはできないだろう。自然生成のものよりも優れたものが生成できる場合でなければ、切り替えは起きない。それが、できて初めて、根本的な「原罪」からの解放が達成される。
根本的な「原罪」からの解放が達成されるまでは、「贖罪」は、課題として残る。
〇国家の役割を考える。
国家の役割は、まず第一に、国家ビジョンの提示である、と考える。
ビジョンなくして、国家像の提示は不可能であり、国家像の提示なくして、国家の仕事を明らかにすることはできないからである。
国家は、その支配領域に住む人間の作るものである。だが、単に、居住する人間が集団になれば、国家となるのではない、と思われる。その人間たちが、集団として、どうその集団を運営していくか、経営していくかを考え、実行することなくして、その集団を維持し、発展させていくことはできない、と考える。
ゆえに、国家は、国家ビジョンを提示する必要がある。
国家ビジョンを提示すると、それに合った実行が問題になる。
国家ビジョンに合った実行には、まず、基礎として、3つの構造が存在している、と考える。
その一つ目は、通貨の発行である。
その二つ目は、通貨の管理である。
その三つ目は、産業の育成である。
以上の三つは、経済面の基礎である。
だが、そもそも、国家成立の前提となる、経済の根幹は、生産と交換である、と考える。
生産は、実物に限らず、精神的なものも含む、すべての客体となるものの生産である。すなわち、原材料とか、農林水産物とか、あらゆる加工品、工業製品のすべて、そして、美術、宗教的営為、芸術的、学術的、電磁的な成果、など、対象となしうるもの全てと、それらを形成することである。
交換とは、生産物の、及び、それに付随する権利の取引、譲り渡し、注文、依頼と提供などと、及び、移動、権利の保障、の確立である、と考える。
経済の根幹は、生産と交換であると考えるが、その二つに横断的に、根幹的にかかわるのが、通貨である。通貨がなくても、生産ができることがあり、交換もできると考えられるが、通貨が確立されることによって、生産も、交換も、確実に、効率的に行われることになるからである。
その通貨は、交換価値や交換体制が確立されなければ、その利用価値は信用できるものにならない。通貨の信用は、かつては金という希少金属の本来的な価値の高さが、それ自体によって、確立するものとなっていた。その利用価値は、基本的に今日でも変化していないので、金は依然として、通貨に近い価値を失ってはいない。だが、法治国家社会の確立によって、金ではなく、国家発行通貨が、法定通貨であることになっているので、法によって通貨と規定されたものが、通貨として通用する、流通することになる。
通貨が確立するために、国家の成立が必要なのである。
今日では、国家が、通貨を確立する。すなわち、国家が通貨を発行する。
そして、その通貨の価値は、有用性の確立にかかっている。その有用性の確立は、まず、その通貨が潤沢に存在していることである。通貨が枯渇してしまっては、経済活動が止まることになるからである。通貨を、潤沢に供給する、その一方で、その通貨によって交換される、物資やサービスが、対応するだけ存在するかどうか、が問題になる。それゆえに、産業の育成が国家の課題になる。
これが、今日の国家の姿である。
よって、通貨の供給と管理と、産業の育成は、国家の重大な責務であることになる。
中でも、国家が確立する通貨、国家が発行する通貨が、今日の経済の根幹にかかわる重大要素なのである。
国家の役割として、居住者、国民の安全保障がある。その実現のためには、医療保健体制、警察防衛体制、消防防災体制の整備がある。
これは、国家の安全保障の基礎である。
これは、国家が世界に一つではないことによって生じる問題でもある。
国家が世界にひとつではないことによって、国家には外交面の問題が発生する。また、外国との交易、対外交渉という問題も発生する。
〇国家経済を考える。
私は、国家経済を、すなわち、「財政」という言葉と同じとは、考えない。しかし、一般に「財政」というと、国家経済のことと理解されている向きがある。だが、財政健全化などという場合に、考えられていることは、国家経済の健全化ではないと思われる。考えられているのは、政府のバランスシートがどうであるか、政府が抱える負債をどうするか、ということである、と思われる。
基礎的財政収支の黒字化が、「財政」の健全化であると考えている人たちもいる。
そういう人たちの考えている、「財政」の健全化とは、税収と支出とのバランスにおいて、税収で支出を賄えているか、ということを問題にしている、と思われる。特に、基礎的財政収支を問題にする場合、その収入とは、税収のことであり、支出とは、国債費を除いた、政策的経費だけのことで、国債の償還費用を含まない、経済政策上のすべての支出の合計ことである、と思われる。
これは、財政法に規定された歳入の定義、また、歳出の定義から、考えているものではない。財政法によると、歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう、とある。
基礎的財政収支の健全化を問題視する人たちが考えているのは、歳入と歳出のバランスのことではない、と思われる。なぜなら、歳入と歳出とは、常に同額になるように調整がされたものであるから。いわゆる歳入不足と言われるのは、正確には、税収不足と言うべきで、歳入は、歳出に合わせて、税外収入、すなわち、公債、つまり赤字国債による収入によって不足が埋め合わされて、同額になるように調整されるものだからである。従って、歳入と歳出との間で均衡が取れないなどということは起きない。常に均衡が取れるように調整される。そのために、赤字国債を発行している。
問題にしているのは、その時々の税収で、その時の政策経費がどれだけ賄えているか、ということだろう。
しかし、単に、ある時点での税収が、その時点での政策経費をどれだけ賄えているか、を問題視するというのは、まったく合理性がない、と考える。
というのは、そもそも税が、政策実行のためにあるのだと考えているとしても、そのために制度設計がされて徴収されてはいないから、である。歳出が、税制の制度設計の前提にされていないから、とも言える。
(ただし、消費税については、社会福祉目的のものと規定され、使用目的が規定された、目的税であるので、それは、その消費税の合計で、社会福祉上の政策経費がどれだけ賄えているかを問題視するのは、合理性がないわけではない。だが、その税収が支出を超えて、黒字になれば、過大徴収、支出がその税収に満たずに黒字になれば、過少支出、となり、どちらの場合も、その税収は、不当な徴収にあたることになる。あるいは、支出が不当なものとなる。)
現行の税は、理念として税とは、政策実行のためにあると考えたり、規定したりしていても、実際には、税を徴収する制度設計において、賄うべき歳出を前提としていない。まず歳出がどうであるから、どれだけの税が必要であるかということを考慮しないで、ただいくらかの税を、ともかく徴収するという、政策や、費用確定の前に、先行的に徴収するという制度設計で制定された徴収方法で、現行の税は、徴収されたものになっている。
このような税収が、さまざまに変化する現実に対応して実行しようという政策の経費を、どれだけ賄えているか、と問題視する。それは、税収で賄うべきなんだから、という固定観念からに過ぎない。また、賄えない分は、赤字国債の発行に頼るのだから、それを認め続ければ、巨額な負債を抱え込むことになり、それは、国の財政を揺るがしかねない重大事だ、と考えるからによる、と思われる。
また、財政収支の健全化が、黒字化ということだとしてみよう。その場合、税収が、支出を上回ることを意味する。支出を上回る税収をあげることが、すなわち、過大徴収が、賄うための税として、合理的であると言えるのか。支出をともかく抑え込んで、税収より下回れば、黒字になる。その場合でも、ただ黒字にすれば、良いことになるのか。支出のために徴収された税を活か切っていないことになるのではないか。また、支出より多くの税を徴収したことになれば、それは不当徴収であることになるのではないか。
あたかも黒字にすれば良いことであるかのように考えるのは、企業会計で、利益をあげるのと同じ発想だからである。赤字になるのは、損失だから、マイナスなんだから、悪であると考え、黒字になるのは、プラスだから、善であると考える。(しかし、税収は、国家にとって、収益行為ではない。税は、利益ではない。)
財政収支の健全化とか、均衡を唱える人たちは、財政赤字になって、その赤字を負債で補って、しかもまともに返済しないで、次々と負債を積み上げ続ければ、いずれ破綻してしまうに違いない、と考えているようだ。だから、悪だ。やめなければならない、と考えているように思われる。
だが、こういう問題意識は、そもそも、通貨とは、国家が発行するもの、国家が発行するから存在するものだ、という事実を認識していないに等しい。
(中央銀行が通貨とされる銀行券を発行するのは、あくまで、国家が制定した法律による。中央銀行が、国家による法の制定の下で行うのである。中央銀行が国家に先行したり、優越したり、上位にあるのではない。その独立性も、国家が制定した法の規定による。国家の制定とは、国会の議決ということである。)
税を、国家の費用、国家の政策的費用とか、国債の償還費用とかを賄うためにあるものだ、と考えるのは、一見、当然のことのように思える。しかし、それは、通貨を発行する能力を持っていない者の発想である。
江戸時代など封建時代においては、米を俸禄とした。米を通貨のように俸給として扱った。米を税として納めさせ、そして、米を俸禄として与えた。そのように、米を通貨のように扱う場合においては、米を好き勝手に作ることはできない。採れた米、または、取り立てた米以上の米を、必要なだけ生み出すことはできない。また、金や金貨を通貨とした場合、金鉱をすべて公有としても、採掘された金以上には金貨を発行することができない。
こういう有限のものを通貨にすると、通貨を管理するほどの権力を持っているとはされながら、実際にある時点での費用を賄えるだけの通貨を、その支払いの時点で、実際に持っているかどうか、それが、物理的に問題になる。だから、費用を賄えるだけの収入、税収があるか、また、負債が巨額になれば、支払い不能に陥るのではないかと、心配することになる。
つまり、不足があるなら、いつでも、必要なだけ通貨を発行して賄うことができる、という発想がない。
しかし、現在は、銀行券という紙幣の時代。さらに、電子的決済の時代になっている。電子的決済とは、実際の紙幣の移動を伴わないで、通貨の収支が行われたとすることである。
ということは、時代的には、既に、通貨は無尽蔵に存在している、ということと同じである、と考えられる。潜在的に、無尽蔵に存在し、発行とは、それを顕在化させる行為なのである。
こういう時代においては、経済政策として考えなければならないのは、無尽蔵にある通貨の流動性の確保である。
そして、無尽蔵に通貨を所有しているのは、国家なのである。国家は、通貨を無尽蔵に、中央銀行に預けているようなものなのである。それを、旧時代的発想で、有限のものと考えて、不足を国債という負債で補い、負債を累積させていくのは、大きな間違いである。また、税は国費を賄うものとして、実際の市中の通貨の量、特に、流動性通貨量がどうであるかによるのではなく、ただ国費を賄うためのものだからと、賄えるだけの税を徴収するというのも、大きな間違いである。どちらも、実際の経済を危ういものにする。
税という回収制度は、実際の通貨の流通量を左右する。だから、通貨の流通量の調節に使うべきものなのである。
また、通貨は、通貨経済社会においては、生存を左右するものなのである。命に関わるものである以上、国家が、国民、居住者の生存を保証する義務があるのならば、通貨経済社会的にそれは、いくらかの通貨の給付を保証するという形で実行されなければ、実効性がないことになる。
〇国家は、国費を、国家発行の通貨で支払う。
その通貨が、税によるものか、新規発行によるものか、国債の販売によって、市中から集めたものかは、問題ではない。
自国通貨発行の国家は、国費を、自国が発行した通貨で支払う。それが、その国家の支払いの最低限の義務であり、その通貨が、税によるものでなければならないという必要や義務はない。必要なのは、その国家が発行した、つまり、自身が発行した通貨、自国通貨であることである。
通貨を発行する国家の義務は、その通貨を普及させることである。なぜなら、その通貨が、経済活動を支える第一の交換手段であると法律の権限をもって規定するのであるから。つまり、発行券を通貨とするのであるから。
〇「義務」とは、何か。
命が基本である。というところから、命を保つためにしなければならないことが、「義務」の始まりである。
命を保つためにしなければならないことが、命の「義務」だ、ということになる。
人であることを保つためにしなければならないことが、人の「義務」だ、といことになる。
社会を保つためにしなければならないことが、社会の「義務」だ、また、社会の構成員の「義務」だ、ということになる。
〇死とは、何か。
死とは、合一である。
自己という存在が、世界に融合、合一して、なくなることである。
死とは、世界との合一である。
世界と合一することによって、世界と不可分となり、世界を認識することができなくなるのである。
〇我々はどこから来て、どこへ行くのか。
我々は、世界から来て、世界へ帰って行くのである。
我々は世界から生まれ、死んで、世界に合一する。
〇神と肉体
何がこの肉体をもたらしたのか。
肉体は、自然がもたらし、自然は、宇宙を含む世界がもたらした。
そして、世界は、何がもたらしたのか。
そう考える時、神的なものの存在に思いを致すことになる。
しかし、人間にとって、基本は、神にあるのではない。
神が基本であるのではない。
人間にとって、基本は、この肉体である。
肉体が、人間にとっての基本である。
その意味で、人間にとって、肉体が神である。
人間にとって、肉体以上の基本はない。
〇存在とは、何か。
存在とは、人間にとって、ほとんど認識である。
その認識とは、感覚と判断である。
感覚しているだけでは、存在を認識しているとは言えない。感覚しているものが何であるかを判断して、初めてそれは存在として、その人間に対して、立ち現れることになる。
それは、空想でも、判断が伴えば、存在になることを意味している。
|